「ママ、今日保育園行きたくない…」
朝の忙しい時間にこの一言。え、ちょっと待って、今から仕事なんだけど!?共働きママにとって子どもの行き渋りは一大事。
でも、実は「行き渋り」は珍しいことではなく、どの家庭でも起こり得ること。そして仕事と育児を両立するママにとっては「行き渋り」をどう乗り越えるかが重要です。
- 子どもの行き渋りの原因と共働きママならではの対応法
- 子育て中のママに向いている柔軟な働き方のオプション
- 行き渋りを経験しながらキャリアを継続できた実例とそのポイント
- 転職を考える際のタイミングと選び方のコツ

保育園では周りの子は元気よく登園してて…娘だけメソメソ。そんな時期もありました。
「行きたくない」の裏側にあるもの
子どもが行き渋る本当の理由
朝の忙しい時間に「行きたくない!」と言われると、つい「早くしなさい!」と急かしてしまいがち。でも、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。
子どもの行き渋りには、様々な理由が隠れています。
分離不安
特に2〜3歳の子どもに多いのが、ママやパパと離れることへの不安。抱っこをせがんだり、泣いてしがみついたりするのは安心感を求めているサインかもしれません。
環境の変化
新しいクラス、新しい先生、引っ越しなど環境が変わると大人でも緊張するもの。子どもにとっても、大きなストレスになります。
人間関係のトラブル
友達とケンカした、誰かに意地悪をされた、先生に叱られた……こうした小さなトラブルが、子どもの「行きたくない」につながることもあります。
体調不良
「お腹が痛い」「頭が痛い」と言っても検温すると熱はなし。こういうとき実は疲れやストレスが原因のことも。うまく言葉で説明できない分、体調不良として現れることがあります。
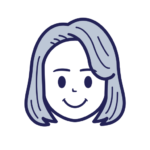
娘が年中の頃に「幼稚園行きたくない」と言い出したことが。理由を聞くと、「○○ちゃんに意地悪されるから」とのこと。先生に確認すると、やはり少しトラブルがあったようでした。
この時、「大丈夫だよ、行きなさい!」と流していたら、娘はもっと嫌な思いをしたかもしれません。でも「嫌だったね」と気持ちを受け止め、先生とも相談したことで少しずつ解決していきました。
子どもの気持ちを受け止めよう
子どもが「行きたくない」と言う時は、その理由に耳を傾けてみることが大切です。「なぜ?」と問い詰めるのではなく「何かあった?」と優しく聞いてみましょう。
ちょっとした声かけで、子どもの不安が軽くなることもあります。行き渋りが続く場合は、先生や専門家に相談するのもひとつの方法。焦らず、子どもの気持ちに寄り添いながら、一緒に解決の糸口を見つけていきましょう。

先生と親でサポート!焦らない、焦らない。
共働きならではの複雑な感情
子どもの行き渋りに直面すると、共働きママならではの複雑な感情が湧き上がります。

「このまま休んだら、大切な会議には誰が出る?」 「また休むなんて、職場の評価が下がるのでは…」 「子どもを無理やり行かせるなんて、ひどい母親?」
こうした葛藤は自然なもの。完璧を求めず、その日できる最善の選択をすることが大切です。私も娘の行き渋りに直面した時、上司に正直に状況を話し在宅勤務に切り替えてもらいました。
子どもの気持ちに寄り添いながらも仕事との両立を図る方法は必ずあります!
行き渋り対応と仕事の両立戦略
即効性のある行き渋り対応テクニック
子どもの行き渋りに対して、即効性のあるテクニックをいくつかご紹介します
1. 朝の準備を前日に済ませる:朝の時間的余裕が心の余裕を生みます。お気に入りの服を前日に選んでおくだけでも、朝のバタバタが減ります。
2. 5分だけルール:「5分だけ行ってみよう」と提案してみましょう。短い時間なら頑張れる、という気持ちになれることも。多くの場合、一度環境に入れば楽しく過ごせます。
3. 選択権を与える:「今日はリュックと手さげ、どっちにする?」など、小さな選択をさせることで主体性を尊重します。
4. 送り出す人を変える:パパや祖父母など、別の人が送り出すと意外とスムーズにいくことも。
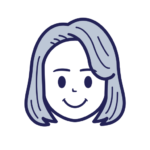
息子が幼稚園に行きたがらない時は、その日の帰りに何をして遊ぶか一緒に決めておくと、楽しみができて行く気になったこともあります!
柔軟な働き方のオプションを探る
子どもの行き渋りに対応するためには、柔軟な働き方を検討することも一つの選択肢です。
在宅勤務を活用する
コロナ禍以降、多くの企業が在宅勤務制度を整えました。子どもの様子が気になる日は在宅で仕事をすることで、緊急時にもすぐに対応できます。ただし、在宅勤務と子育ての両立には明確なルール作りが必要です。
「子どもがいる時間は仕事をしない」「オンライン会議の時間は特別なおもちゃで遊べる時間にする」など、子どもと仕事の境界線を作りましょう。
在宅勤務についてはコチラの記事でまとめています↓
時短勤務・フレックスタイム
時短勤務やフレックスタイムを利用することで、子どもの送り迎えに余裕を持たせることができます。特に行き渋りがある時期は、少し遅めの出社にしてもらうなど、上司と相談してみるのも一案です。
ワークシェアリング
同じポジションを複数人で分担するワークシェアリングという働き方もあります。例えば、月・水・金はAさんが、火・木はBさんが担当するという形です。子どもの調子に合わせて勤務日を調整できる柔軟性があります。
キャリアを諦めない選択肢
子育てに理解のある職場への転職
現在の職場が子育てに理解がなく、両立が難しいと感じるなら転職も選択肢の一つです。
- 企業の育児支援制度を確認する: 育休・時短勤務の実績、在宅勤務制度など。
- 実際に働いているママの声を聞く: 口コミサイトや知人のネットワークを活用。
- 面接で子育てとの両立について質問する: 企業の本音が見えてきます。
子育てママの転職についてはコチラでまとめています↓

娘も2歳ごろ特に行き渋りが多く、毎朝のように泣かれる日々が続きました。私自身も「仕事に行かなければ」という焦りと、娘を置いていく罪悪感に押しつぶされそうになり、涙が出ることもありました。朝から私がシクシク泣き出して先生もびっくりw
思い切って上司に相談し、筆者の場合は在宅勤務制度を活用することで状況は大きく変わりました。朝のバタバタが減り、娘と気持ちを落ち着けて過ごせる時間が増えたことでスムーズに送り出せるように。結果的に子どもも私も前向きな気持ちで一日をスタートできるようになりました。
その時々によって悩みは変わるもの。ライフステージに合った働き方を模索していきましょう!!
スキルアップで選択肢を広げる
新しい働き方を実現するには、スキルアップも重要です。特に需要の高いITスキルや資格取得は、在宅ワークの可能性を広げます。
- Web制作・プログラミング: 在宅で働きやすい定番スキル
- ライティング・編集: 時間や場所に縛られにくい
- オンライン英会話講師: 子どもが寝た後の時間を活用できる
子どもも親も笑顔になる工夫

ママ・パパがニコニコしてると、子どもも安心感100%!
親子の時間を質で勝負
忙しい共働きママにとって、子どもとの時間は量より質が重要です。短い時間でも、集中して向き合うことで子どもの安心感につながります。
- 朝の支度を一緒にする「チームワーク時間」 一緒に着替えたり、朝食を準備したりすることで楽しく支度ができます。
- 帰宅後の「ノーメディア・ノースマホ30分」 帰宅後の30分はスマホを手放し、子どもとじっくり向き合う時間に。
- 寝る前の「今日あったことトーク」 1日の出来事をお互いに話し合うことで、親子の絆が深まります。
こうした親子の特別な時間は、子どもの安心感につながり、行き渋りの解消にも繋がります。
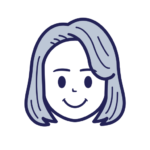
「今日あったことトーク」 はお風呂でも。娘の話は止まりませんw
自分時間を確保する罪悪感ゼロ作戦
子育てと仕事の両立に加え、自分の時間を確保することも重要です。「自分の時間を取ると子どもに申し訳ない」という罪悪感は手放しましょう。
筆者は月に一度「ママの充電日」と決めて、好きなカフェで読書したり友人と会ったりしています。たった半日でも心がリフレッシュされ、子どもにも笑顔で向き合えるようになります。

親が笑顔でいることが、子どもにとっても一番の安心材料。無理せず、自分に合ったペースで日々を乗り越えていきましょう。
まとめ:行き渋りを乗り越え、新しい働き方を見つける
子どもの行き渋りは、親にとって大きなチャレンジですが、同時に新しい働き方を模索するきっかけにもなります。完璧を目指すのではなく、その時々でできることをする。そして何より、子どもの気持ちに寄り添いながらも、自分自身のキャリアを大切にする姿勢が、結果的に子どもの未来にも良い影響を与えるでしょう。
- 子どもの「行きたくない」には必ず理由がある: 急かすのではなく、まずは気持ちを受け止めることから始めましょう。
- 柔軟な働き方は選択肢の一つ: 在宅勤務やフレックスタイム、時には転職も視野に入れてライフステージに合った働き方を模索しましょう。
- 完璧なママを目指さない: 仕事も子育ても、その日できる最善を尽くせば十分。自分を責めず、自分時間も大切にしましょう。
「行きたくない」と言われた朝、少し早起きして子どもとじっくり向き合う時間を作る。そして在宅勤務を活用して、お迎えの時間も少し早める。そんな小さな工夫の積み重ねが、子どもも親も笑顔にする道につながるのではないでしょうか。

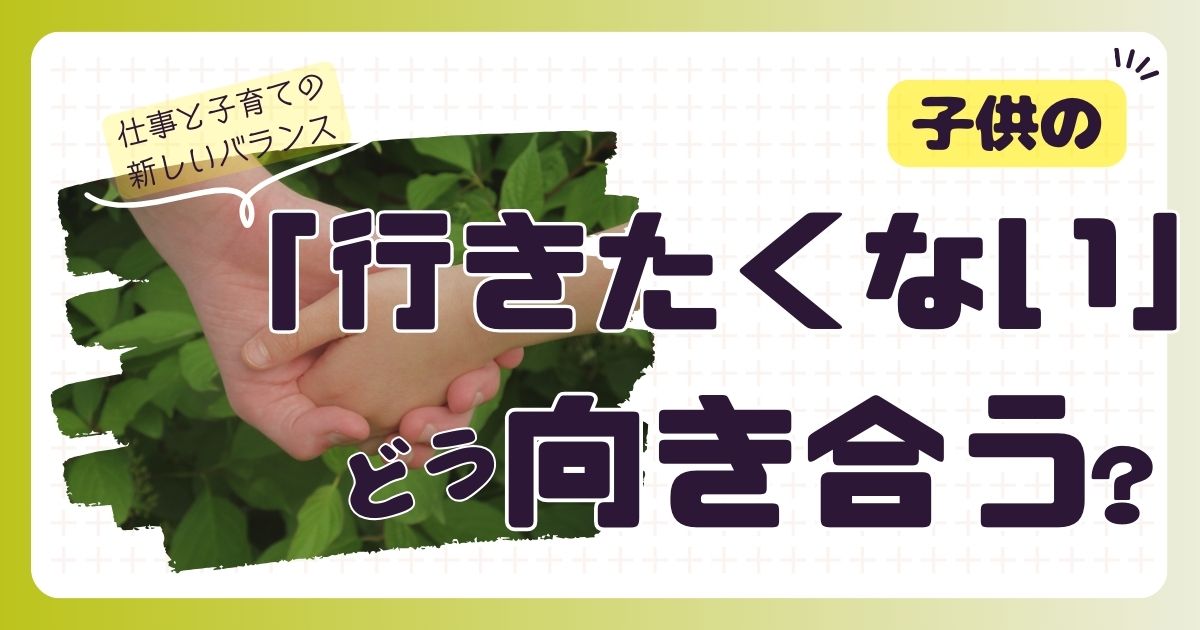





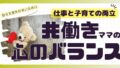
コメント